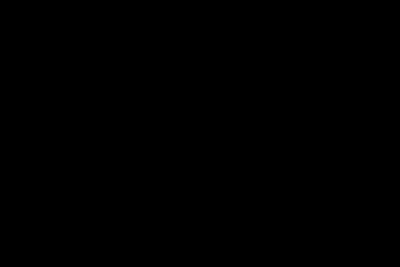昭和20年8月9日、B29から投下された原子爆弾「ファットマン」は、松山町171番地の上空500mで炸裂した※1。
爆発によって生じた凄まじい爆風と熱線は、僅か数秒の内に長崎市の町を荒野へと変えた。
一本柱鳥居

爆心地から800m地点に鎮座する山王神社の参道には、かつて四基の鳥居が存在していたが、現存するものは二の鳥居のみである。
爆風によって鳥居の左半分が吹き飛んだものの、奇跡的に倒壊は免れた。片足で立つ鳥居の姿は、原子爆弾の威力を物語っている。

二の鳥居は、長崎原爆遺跡に指定され保存されている。
この鳥居は、1924年(大正13年)10月に山王神社の二の鳥居として建てられたが、1945年(昭和20年)8月9日、午前11時2分、原子爆弾のさく裂により、一方の柱をもぎ取られてしまった。ここは爆心地から南東へ約800mの距離にあったが、強烈な輻射熱線によって鳥居の上部が黒く焼かれ、また爆風によって一方の柱と上部の石材が破壊され、上部に残された笠木は風圧で反対方向にずれている。
ただ一個の原子爆弾によって、当地区もまた、ことごとく灰じんと帰したが、この鳥居は強烈な爆風に耐え、あの日の惨禍を語りつぐかのように、いまなお一方の柱で立ち続けている。しかし、その後長い年月を経たため、安全性を考慮して柱の基礎部分や接合部分の補強工事を行った。
長崎市はこの地で亡くなられた方々のご冥福をお祈りし、二度とこのような惨禍が繰り返されないことを願って、この銘板を設置する。
安全性を考慮し補強工事が行われているが、姿形は当時のままである。

吹き飛んだ鳥居の左半分は、参道の脇に現存している。

割れてしまった額束。間近で見ると非常に大きい。

倒壊した三の鳥居の柱の一部は「坂本町民原子爆彈殉難之碑」として残っている。

原子爆弾の投下によって、社殿は跡形もなく吹き飛んだ。
現在の山王神社の社殿は、昭和25年に再建されたものである。
被爆クスノキ

境内の入口に根を下ろす2本の巨大な楠の木。
原子爆弾の強烈な熱線によって丸焦げとなった楠の木は、完全に枯死したと思われていた。しかし、その後再び新芽を芽吹き、次第に樹勢を盛り返し奇跡的に蘇った※2。
被爆した楠の木は長崎市の天然記念物に指定され、平和と再生のシンボルとして親しまれている。

楠の木の根元に、大きな石と案内板がある。
この石は、平成十八年(二〇〇六年)山王神社被爆楠の木の二度目の治療の時に、右側の木の空洞の中から取り出されたものです。
(爆風 秒速二二〇メートル、熱線二〇〇〇度<推定>)その証として無数の石が、右側の木の中から発見されました。
この木の三メートル上にのぞき窓があり、この部分に空洞があって爆風により石が舞い上がり、小石が穴の中に入ったものと考えられます。
常識では考えられないような大きな力が加わった原子爆弾の威力を物語っています。
神社に向かって左側の楠の木は爆心地に近く、主幹は途中で折れています。そのうえ、木の幹(内部)には無数の破片(瓦、金属、小石等)が突き刺さっていた為、治療の時その破片を取り除くのには困難を極めました。
階段を上って樹洞を覗くことが出来る。

樹洞を覗いてみると、確かに小石が大量に残っていた。仄かに香る楠の匂いが心地良い。

楠の木に別れを告げ、再び参道を通り帰路に就く。復興を経て、長崎市の町並みは当時と随分変わってしまった。
令和へと時代は移り、戦争を経験した世代の者たちは減少し、戦争の記憶の風化が懸念されている。二度と同じ過ちを繰り返してはならない。一本柱鳥居は、あの日の惨禍を知る語り部として、その身をもって後世へ戦争の記憶を伝え続けている。
廃墟評価
| 廃墟退廃美 | – |
| 到達難易度 | C |
| 廃墟残留物 | – |
| 崩壊危険度 | – |
| 廃墟化年数 | – |
廃墟評価の詳細はこちら。
脚注
※1^ 【長崎の原爆 | 調べる | ながさきの平和-11時2分】
“爆発は、目標地帯からおよそ5~600メートル北方にそれて、松山町171番地のテニスコートの上空で起こった”
https://nagasakipeace.jp/search/about_abm/scene/1102.html
※2^ 【山王神社公式ウェブサイト-山王神社の被爆の話し】
“昭和20年の原爆で主幹の3分の1以上を失ったため、 樹高は10メートル内外ですが、四方に張った枝は交錯して一体となり、東西40メートル、南北25メートルの大樹冠を形成しています。原爆被災により一時落葉し枯れ木同然になったにも係わらず、2年程度の後、奇跡的に再び新芽を芽吹き、次第に樹勢を盛り返し今日に至っています”
https://sannou-jinjya.jp/pages/17/